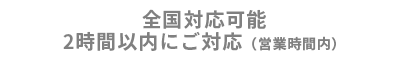「試作スピード」が命綱~ 開発を加速させる時短テクニック集~
「試作が思ったより遅くて、発売スケジュールがズレた…」そんな経験はありませんか?
特にスタートアップや新規事業では、スピード=競争力。
試作や開発に時間がかかると、資金繰りや商機に直結して影響します。
本記事では、スタートアップが開発を加速させるための“時短テクニック”を3つご紹介します。
明日から実践できる工夫ばかりなので、ぜひチェックしてみてください。
開発スピードを高める3つのテクニック
1. 最短“翌日出荷”が可能な体制を選ぶ
試作依頼の納期が「2〜3週間先」では、スタートアップにとって致命的です。
時間がかかる理由は、社内で加工設備を持たず外注依存になっている場合が多いから。
たとえばクロスエフェクトでは、3Dプリントや真空注型などを自社内で完結できる設備を整えており、案件によっては最短翌日出荷も可能。
この“スピード納品”は、製品化スケジュールの短縮に直結します。
2. 社内一貫体制で外注によるタイムロスを減らす
開発の現場では「設計はA社、加工はB社、仕上げはC社」という分業型フローが一般的です。
しかし、この方法では工程間の連絡・確認・輸送に時間がかかり、結果として納期が延びます。
設計〜試作〜仕上げをワンストップで行える体制なら、
・工程間のやり取りが最小限
・設計変更も即日反映
・品質の一貫性も確保
というメリットがあり、結果的に大幅な納期短縮につながります。
3. 設計データを“早めに共有”し、意思決定を前倒し
スタートアップでは人数が少ない分、意思決定の遅れが全体スケジュールに直結します。
「設計がほぼ固まってから共有する」よりも、途中段階でも早めに情報共有することで、仕様確認や修正を同時進行できます。
ポイントは、
・図面や3Dデータを早い段階で共有
・チェック項目を事前に明文化
・定期的なオンラインレビューを設定
この仕組みを入れるだけで、試作のリードタイムは確実に短縮されます。
まとめ|“早い”は最大の武器になる
スタートアップにとって、開発スピードは命綱です。
1、納期短縮できる製造パートナーの選定
2、社内一貫体制の活用
3,設計共有の前倒し
この3つを意識することで、開発の流れは大きく変わります。
クロスエフェクトでは、スタートアップ支援の豊富な実績を活かし、スピードと品質を両立した試作体制をご提供しています。
「とにかく早く試作したい」「今のスケジュールを短縮したい」という方は、ぜひお気軽にご相談ください。
高速試作品製作についてはこちら
製品のご相談やプレミアムファクトリーツアー(工場見学)も随時受付中です。工場見学のお申込みはこちら
案件相談のお問い合わせは📩 こちら
関連リンク